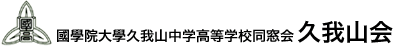佐々木周二先生の思い出Reminiscence

-

母校キャンパス前庭で生徒たちと語らう
(昭和51年・先生64歳) -

勲三等瑞宝章受章の日、皇居参内前に国立劇場でのご夫妻
(昭和59年・先生72歳) -

平成8年撮影の肖像写真
(先生83歳)
佐々木周二先生 略歴
【学歴等】
| 明治45年6月24日 | 宮城県に生まれる |
|---|---|
| 大正8年4月 | 宮城師範学校附属小学校入学 |
| 大正10年5月 | 京城桜井小学校編入 |
| 大正11年4月 | 京城南大門小学校転入 |
| 大正14年3月 | 京城南大門小学校卒業 |
| 大正14年4月 | 京城中学校入学 |
| 昭和6年4月 | 東京府立第四中学校復学 |
| 昭和8年4月 | 日本大学第二中学校編入 |
| 昭和10年3月 | 日本大学第二中学校卒業 |
| 昭和11年4月 | 東京高等師範学校入学 |
| 昭和15年3月 | 東京高等師範学校卒業 |
| 昭和15年4月 | 東京文理科大学教育学科入学 |
| 昭和17年9月 | 東京文理科大学教育学科卒業 |
| 昭和17年10月 | 東京文理科大学教育学科研究科入学 |
| 昭和19年3月 | 東京文理科大学教育学科研究科卒業 |
【職歴等】
| 昭和17年10月~昭和19年3月 | 岩崎学園開設準備室委員 |
|---|---|
| 昭和19年4月~昭和23年3月 | 岩崎学園久我山中学校教諭・教頭 |
| 昭和23年4月~昭和24年3月 | 岩崎学園久我山中学校・久我山高等学校教頭 |
| 昭和24年3月~昭和24年8月 | 久我山学園久我山中学校・久我山高等学校教頭 |
| 昭和24年3月~昭和25年11月 | 久我山大学教授兼任 |
| 昭和24年8月~昭和24年10月 | 久我山学園久我山中学校・久我山高等学校校長代行学園理事 |
| 昭和24年11月~昭和27年9月 | 久我山学園久我山中学校・久我山高等学校校長 |
| 昭和27年2月~昭和29年10月 | 久我山学園幼稚園園長 |
| 昭和27年9月~昭和63年3月 | 國學院大學久我山中学校・高等学校校長 |
| 昭和29年10月~昭和57年4月 | 國學院大學附属幼稚園園長 |
| 昭和32年4月~平成11年4月 | 学校法人國學院大學理事 |
| 昭和35年4月~平成6年3月 | 國學院大學栃木高等学校校長 |
| 昭和38年3月~昭和62年4月 | 学校法人國學院大學栃木学園理事長代行・常務理事 |
| 昭和40年4月~昭和54年5月 | 國學院大學栃木二杉幼稚園園長 |
| 昭和41年4月~平成23年4月 | 國學院大學栃木短期大学学監 |
| 昭和57年4月~平成23年4月 | 國學院大學附属幼稚園名誉園長 |
| 昭和62年4月~平成11年4月 | 学校法人國學院大學理事長 |
| 昭和62年4月~平成15年3月 | 学校法人國學院大學栃木学園理事長 |
| 昭和63年4月~平成23年4月 | 國學院大學久我山中学校・高等学校名誉校長 |
| 平成4年4月~平成8年3月 | 國學院大學幼児教育専門学校校長事務取扱 |
| 平成6年4月~平成23年4月 | 國學院大學栃木高等学校名誉校長 |
| 平成11年4月~平成23年4月 | 学校法人國學院大學常任顧問 |
| 平成19年4月~平成23年4月 | 学校法人國學院大學栃木学園長 |
| 平成23年4月26日 | 逝去 享年98歳 |
【関係団体等】
| 社団法人日本私立大学連盟理事(昭和62年5月~平成11年4月) |
| 社団法人日本私立大学連合会会計監査(昭和62年6月~昭和63年3月) |
| 財団法人私学研修福祉会評議員(昭和63年9月~平成6年9月) |
| 財団法人私立大学退職金財団評議員(平成4年9月~平成9年10月) |
【賞 歴】
| 東京都知事表彰(学校教育功労)(昭和47年10月) |
| 栃木市特別功労者受賞(昭和55年5月) |
| 勲三等瑞宝章受章(昭和59年11月) |
佐々木周二先生の思い出を綴る
佐々木周二先生が遺したもの
久我山会第3代会長 佐々木 博(1期) 先生との出会いは、昭和十九年一月の冬晴れの日でした。まだ工事中の久我山中学校に入学願書を提出するため、母と共に訪れたときでした。黒い詰め襟の服を着た若き日の佐々木周二先生に声をかけられました。何を話されたのかは覚えていませんが、先生の柔和な笑顔は今でもはっきりと思い出されます。
入学してみると、先生は英語の先生でした。いつも長い竹の棒を持って教室に入ってこられましたが、声を荒げて生徒を叱ることはなく、諄々と諭すように話されました。先生は事ある毎に「君たちは一期生である。君達の歩いた道を後輩たちはついてくる。そのことを自覚して行動しなさい。やがて、それが伝統となって後輩に受け継がれていくのだ」と語ってくださいました。そのため、私たちの心に自然と一期生であるという自覚が染みこんでいきました。教育者としての先生には、人を引き付ける魅力があり、やがて、一期生のカリスマ的存在となりました。 学園経営者としての先生は、いつも将来を見つめた素晴らしいアイディアの持ち主でした。創立十五周年記念日を過ぎた頃、同窓会の幹部を呼んで「恩師と卒業生との交流会の場として、毎年正月に新年名刺交換会を催しなさい」と指示されました。早速、準備を始め、アトラクションとして、餅つきをやろうと決めました。餅つきの道具一式は、学校近くの卒業生の家から借りてきて、昭和三十七年正月に第一回新年名刺交換会が実現しました。学園設立者岩崎清一先生もご来場くださって、一緒に餅をつかれました。その後「新年交歓パーティー」と名称を改めて、今日まで毎年欠かさず続いております。
ある時、先生は私に「人は、昔お世話になった恩師の墓参りがしたくなることがある。その時、恩師の墓が何処にあるか判らないようではいけない。久我山の卒業生には、思いついた時いつでも恩師の墓参りができるように、歴代の恩師の霊を納めた墓を建てたい」と語ってくださいました。そして、岩崎清一先生のご逝去を機に、世田谷区北烏山の西蓮寺に「学園の墓」が建立されました。毎年、創立記念日の前日に、新しく物故された方が、分骨され納められます。
墓碑には、先生の思いを託した四行の詞が刻まれています。
「学園をつくり
学園をそだて
学園をまもり
学園を愛しつづけた人びと ここに眠る」
折々の思い出
久我山会第5代会長 岸 輝雄(7期) 昭和二十四年の夏、小学六年生だった私は、担任教諭から「開校間もないが教育については立派な考え方の中学があるから受験してみないか」と薦められたのが岩崎学園久我山中学校でした。翌二十五年春、桜花に迎えられて入学した時、入れ替わりに第一期生が卒業して行かれました。
入学式で初めて佐々木先生にお目にかかり「若い校長先生だな」というのが第一印象で、後に英語を教えて頂き、その中でも「タイムイズマザー」の言葉が今でも頭に残っています。
卒業後、先生との邂逅は思いがけないものでした。大学卒業後、ホテルマンを志し研修中の熱海のホテルに、奇遇にも母校の教職員全員が宿泊したのです。先生は、「ここにも卒業生が頑張っているぞ」と私を紹介してくださり、その日の夜は大宴会で、先生の音頭で「お手手つないで」の大合唱でお開きとなりましたが、先生のスケールの大きさに圧倒されたものでした。
その後、七期会の会長となり、卒業三十周年記念の名簿発行の際には題字を揮毫して頂き、更に四十周年の時には、来賓の恩師に贈呈する「久我山音頭」の銅版楯の作成の許可を頂きに伺った折、「今まで誰も言ってこないからその権利を君に上げるよ」と、快諾を頂きました。楯が完成して先生にお届けすると、作詞者の岡野弘彦先生にも差し上げたいので届けて欲しいと言われ、國學院大學の理事長室までお届けしたことや、七期会の前日お電話を頂き、転んで怪我をして出席出来なくなったので、お祝いを取りにきて欲しいとのことでご自宅へお伺いして過分なお祝いを頂戴したりなど、折々の思い出は尽きません。
また、久我山会会長に就任後ご挨拶した時、「会長さんは大変だが卒業生が疎遠にならないよう橋渡しを頼む」と優しいお言葉をかけて頂いたのが、昨日のように思い出されます。 先生は、同窓会生みの親として卒業生に絶えず気配りしてくださり、関西久我山会、神職関係同窓会も先生の肝いりで結成されました。卒業生の近況報告には「おおそうか、頑張っているな」と満面の笑みで励ましてくださり、皆は先生のこの一言と笑顔にどれほど元気を頂いたことでしょう。
教育者と事業家、この両面の見識を持たれ、戦後の到底言い尽くせない苦難を乗り越え、学園を開花させ、卒業生が胸を張って誇れる今日の母校に育て上げてくださいましたことに、心より感謝申し上げます。
安らかにお眠りください。そして母校の更なる発展と卒業生の活躍をお見守りください。
(以上2編は、母校「校報」佐々木周二先生追悼特集号より転載)
佐々木周二先生『私学の歳月』から
※年月は「校報」掲載月です
教頭 佐藤誠博- ① わが落第記/令和2年10月
- ② 自分から/11月
- ③ クラブの姿/12月
- ④ 私のねがい―厳しく鍛えよ―/令和3年1月
- ⑤ 親を大事にしなさい/2月
 <佐々木周二先生『私学の歳月』から ① ~ ⑤>
<佐々木周二先生『私学の歳月』から ① ~ ⑤>
- ⑥ 教育の庭/令和3年3月
- ⑦ 創立当時/6月
- ⑧ 心の力/7月
- ⑨ ルールを守れ/9月
- ⑩ 汗を流せ/令和4年2月
 <佐々木周二先生『私学の歳月』から ⑥ ~ ⑩>
<佐々木周二先生『私学の歳月』から ⑥ ~ ⑩>