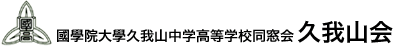学校長挨拶Greeting
創立80周年記念式典式辞
昭和19年、創立者・岩崎清一先生が、ここ久我山を開校の地と定めて以来、早80年の歳月が流れました。学び舎の移ろいを見守ってきた欅並木も、秋の訪れに色づき始めたこの佳き日。創立80周年という節目の記念式典を、学校法人國學院大學理事長・佐栁正三先生をはじめ来賓各位のご列席のもと、生徒・教職員とともに挙行できますことは、学園の一員としてこの上ない慶びです。あわせてこれまで学園とともに歩み、支えて下さったすべての方々に、深甚なる謝意を表します。
創立記念日は、学園の歴史と創立当時の関係者の思いを振り返り、今を生きる私たちが更なる発展に向けて何ができるか、何をすべきかに思いを巡らす日です。明日の創立記念日を迎えるにあたり、本校のたどってきた道のりを、今一度振り返ってみましょう。
昭和19年、岩崎先生の祖国復興にかける熱い思いから、岩崎学園久我山中学校は創立されました。しかし太平洋戦争末期、戦況は悪化の一途をたどり、同20年3月の東京大空襲では、東京都の半数以上の学校が戦禍を被ります。創立2年目の本校は、幸いにも校舎の被害も最小限で済み、9月には2学期の授業を再開することができました。しかし当時の学園母体であった岩崎通信機は経営環境の激変から、危急存亡の淵に立たされます。その余波のため学園の財政も、予断を許さない状況に立ち至りました。
そのような中、終戦に伴う教育制度改革によって、本校でも新制中学への移行、中学校女子部・新制高校の開設と、新しい時代に向けて様々な改革がなされていきました。創立以来、学園の母体であった財団法人「岩崎学園」が「久我山学園」と改称されたのもこの頃です。
折しも、教育制度改革の一環として都内の公立中学校が急速に整備・拡充され、収容生徒数も大幅に増加しました。このことが当時の私立中学・高等学校の運営に与えた影響は非常に大きなもので、久我山中学校でも昭和27年3月には、生徒募集中止のやむなきに至りました。
一方、学制の改革により、現在の教養課程にあたる予科が廃止された私立大学は、それに代わる付属の高等学校の設置を進めており、久我山学園にも幾つかの大学から打診がありました。その中で東京都の斡旋により、國學院大學と久我山学園の間で合併の交渉が開始されます。そして、昭和27年8月28日、学校法人國學院大學の評議員会において久我山学園の吸収合併が議決され、本校は法人傘下の教育機関として、新たな歩みを始めることとなりました。
合併が成功した最大の要因が両法人の建学の精神の一致にあったことは、言うまでもありません。校歌に「いかで忘れむ もとつ教は いよゝみがかむ もとつ心は」と謳われるように、古より受け継がれてきたわが国の文化を学び、新たな時代を生きていく糧としよう、との志を一にすることから、成し遂げられた合併でした。
合併間もない昭和29年度当初の生徒在籍数は、中学高校合わせて355名でしたが、同33年度には1000名を超えます。しかし、その後の学園の歩みは、必ずしも順風満帆ではありませんでした。昭和30年代末頃までの在籍生徒数の推移を見ると、当時の佐々木周二校長を始めとする教職員の方々が、学校経営にあたって大変苦慮されたであろうことが推察されます。
しかし、そうした中で昭和30年代半ば以降になると、現在に至る「学園のかたち」が少しずつ整い始めます。昭和34年の体育館竣工を始めとして、高校1年次の研修会やクラブ活動の開始、久我山祭の再開、理科会館竣工と続きます。そして前々回の東京オリンピックが開催された昭和39年、久我山は創立20周年を迎え、その2年後には本館校舎が完成しました。
昭和50年代に入っても、第2体育館、文科会館、西2号館第1期工事の竣工と施設の整備は続き、昭和60年には中学募集を再開、高校女子部を開設します。そして平成3年の中学女子生徒入学をもって、男女別学・中高一貫体制の完成を見ました。
顧みれば創立以来、数多くの生徒・教職員や関係者の方々のご苦労の上に現在の久我山があるのだ、との思いが胸に湧いて参ります。そして10年、20年後の学園の姿を思い描く時、学校法人國學院大學傘下の教育機関として建学の精神を体しつつ、我々が目指す「学び」の実現に向けて歩みを続けることへの責任の重さに、改めて身の引き締まる思いがいたします。
結びにあたって、生徒・教職員がともに学校生活を営めることを、今日まで学園に関わってこられたすべての皆様に、重ねて感謝申し上げます。そして先人の志を胸に刻みながら、久我山での学校生活の更なる充実と、学園の益々の発展を祈念して式辞といたします。